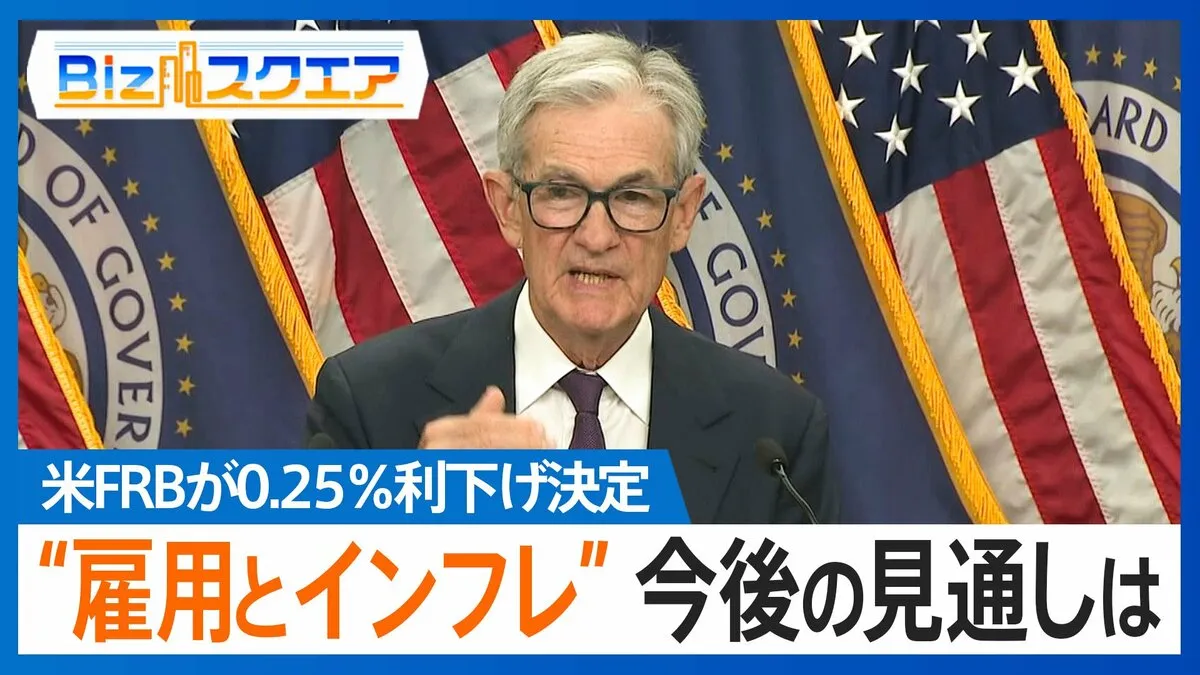
0.25%の利下げを決定した米FRB。為替相場は一時145円台まで円高が進むも、急転し再び円安に。その背景にあったのは…?そして、利下げでアメリカの“雇用とインフレ”はどうなる?
【写真で見る】「ドルを売っていた人が慌てて買い戻した」米FRB・9か月ぶりの利下げも「円安」ナゼ?
トランプ氏指名の理事だけ「反対票」
アメリカの中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は17日、金融政策を決める会合で4.5%を上限としていた政策金利を0.25%引き下げることを決めた。
金利の引き下げは2024年12月以来、6会合ぶりで、第2次トランプ政権のもとでは初めてとなる。
FRBパウエル議長:
「失業率は低水準を維持しているもののわずかに上昇し、雇用増加ペースは鈍化、“雇用の下振れリスクが高まった”。“リスク管理のための利下げ”と捉える事ができるだろう」
0.25%の利下げには、投票権を持つ12人のうち11人が賛成。
トランプ大統領の指名で理事に就任したばかりのミラン大統領経済諮問委員会委員長だけが、0.5%の大幅な利下げを主張し反対票を投じた。
利下げで為替急転「円高⇒円安」ナゼ?
利下げを受け、17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は260ドル上昇。
18日の日経平均株価も一時700円以上値上がりし、終値として史上初めて4万5000円を超えた。
一方、外国為替市場では利下げ決定で円高が進み145円台に。ところが、なぜかそこから急に147円近くまで円安が進んだ。
その理由は何なのか…?
番組の為替予想でおなじみの花生さんは、「パウエル議長の発言」にあると話す。
『バルタリサーチ』花生浩介さん:
「パウエル議長は“予防的な利下げ”だと言った。継続的にどんどん利下げをするかどうかよくわからないと。とりあえずは1回やってみて、データ次第でどちらでも動けるようにしておくというような、予防線を張っているというイメージに記者会見の印象としては捉えたので、それでドルを売っていた人が慌てて買い戻した」
パウエル議長が利下げに慎重な姿勢を示したことで、債券市場にも影響が出ているという。
花生さん:
「債券市場が注目しているのは、関税を中心とするトランプ氏の経済政策でインフレが起きないのだろうかということ。まだあまり決め打ちできていない。一方で、株式市場はもうちょっと楽観的で、インフレも最優先課題ではなくなったという感じで捉えていて、株は上がるけど、債券はそれほどまでいかず、為替市場も債券市場に合わせる形でドル売りに迫力がないと、そんな状況」
今後の株価、為替、債券市場、そして景気の先行きはどうなるのか。
FRBは今後の政策金利について年内にさらに0.5%、通常の0.25%ずつの利下げ幅なら“あと2回利下げをする”との見通しを示している。
利下げ判断は「理解できる」
2022年のウクライナ危機もありインフレが急伸したアメリカ。
FRBは政策金利を大幅に引き上げ、2024年後半になって3回の利下げを実施。その後は据え置かれた状態だったが、9か月ぶりに利下げが再開された。
今回の利下げのタイミングや理由について、日銀政策委員会の審議委員を務めた白井さゆりさんは「理解できる」と話す。
【FRBパウエル議長】(17日)
▼“雇用の下振れリスク”が高まっている
▼(利下げは)1回限りの手段ではない
▼リスクに対する“保険”のための利下げ
▼“雇用と物価の両面のリスク”を抱えた状況
――物価と雇用と両面を睨んできたわけだが、雇用の方が若干心配になったというのがパウエル氏の理屈だ
『慶應義塾大学』総合政策学部教授 白井さゆりさん:
「雇用者数の伸びが、下方修正もあって5月からかなり悪くなっている。レイオフ(一時的な解雇)の件数や新規失業保険申請者数も増えている。移民の労働者が少なくなっているので供給も減っているが、労働者への需要も減っているということで、パウエル氏が労働市場に重点を置いたというのは理解できる」
トランプ関税で「インフレ」にならないワケ
一方で、FRBはトランプ関税によるインフレも警戒している。直近で、物価は少し上がってきている状況だ。
【米・8月の消費者物価指数】
▼総合:前年同月比2.9%
▼コア指数(食品・エネルギー除く):3.1%
・食品:3.2%↑
・新車:0.7%↑
・衣類:0.2%↑
『慶應義塾大学』総合政策学部教授 白井さゆりさん:
「ガソリンの価格が下落しているのでその分抑えられている面もある。また、パウエル氏も言っていたように関税分はみんなほぼ価格転嫁しているが、フル転嫁ではなく、大体60~80%ぐらいの転嫁と言われている。その分小売業者や流通業者が利益を抑えて消費者に転嫁していないので、思ったほど大きなインフレになっていない」
消費がそこまで強くないから価格を上げられない、ということだがアメリカの景気は悪くない。
アトランタ連銀が発表する「GDP Now」を見ると、7-9月期のGDP伸び率は3.3%と堅調。(※17日時点の予測)
個人消費は2.7%、設備投資は11.9%と上向きだ。
景気の先行指標、ISM(景況感指数)やPMI(購買担当者景気指数)も、“景気拡大”を示す数値で、小売売上高も3か月連続増加と個人消費は堅調に見える。
【米・8月の経済指標】
50超=景気拡大/50割れ=景気後退
▼ISM(景況感指数)⇒【製造業48.7】【非製造業52.0】
▼PMI(購買担当者景気指数)⇒【製造業53.0】【非製造業54.5】
▼小売売上高⇒7320億ドル/前月比0.6%増
※全米供給管理協会、米S&Pグローバル、米商務省より
白井さん:
「実はアメリカの経済はかなり良い。価格転嫁が難しいという話と矛盾するように見えるが、低所得者や中所得者はかなり苦労していると思うので、その人たちに価格転嫁できないということ。ただ、大金持ちはもっと大金持ちになっていて消費がすごく活発なので全体としてはすごく消費が伸びている」
――そうなると、FRBが慌ててどんどん利下げするほど追い込まれた状況ではないと
白井さん:
「なので、今回の利下げでなぜ市場の反応がイマイチだったのかというと、思ったほどトランプ政策の影響が強く出なかったから」
米経済は「ソフトランディング」に?
利下げと同時に、FRBは今後の経済の見通しも発表している。
【2025年FOMC経済見通し】※()内は6月の予想からの増減
▼物価上昇率:3.0%(±0)
▼GDP成長率:1.6%(+0.2)
▼失業率:4.5%(±0)
▼政策金利:3.6%(-0.3)
――利下げしておきながら、GDP成長率は多少上がるけど、失業率と物価上昇率は変わらないですよと言っているようにみえる
『慶應義塾大学』総合政策学部教授 白井さゆりさん:
「一見そう見えるが、利下げ分も織り込んだ上で、失業率はもっと上がるところを抑えられた。成長率はむしろ上がる方向に上方修正されていて、インフレの方は相互関税率の引き上げもあって上昇していくけれども、思ったほど価格転嫁していないのでその分で抑えられるという見通しになっている」
つまりは、ソフトランディングのシナリオをFRBが描いているということだという。
年内利下げ「あと1回の可能性も」
では、今後の利下げの見通しはどうなのか?
FOMCの参加者19人による政策金利の見通しを見ると
【2025年末の金利を9人が3.6%と予測】⇒年内残り2回の会合で、通常ペースの2回分に当たる0.5%の利下げを見込んでいることになる。
一方で、年内に更なる利下げは必要とないとしているのが7人。FRBの中でも意見が割れているということなのだろうか。
『慶應義塾大学』総合政策学部教授 白井さゆりさん:
「19人のうち投票権を持つのは12人で、実際にどうなるか本当にわからないぐらい、今のアメリカ経済の判断は難しい。8月に関税率が引き上げられて、今のところは転嫁率は大きくないが、今後どうなっていくかわからない。利下げをして経済も良くなるから、一応あと2回ということになっているけども、1回になる可能性もあると思う」
――アメリカ経済の今後を見る上で、一番心配な点は?
白井さん:
「やはり今、失業者数が増えていてレイオフの数も増えているので、労働者への需要が弱いということ。そこのところがこれからも持続するかというのが、利下げをする上で重要なポイントになる」
(BS-TBS『Bizスクエア』2025年9月20日放送より)
・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】
・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」
・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市

